「教会の聖人たち(下)」(中央出版社、\4,500)P136-141より/聖母の被昇天
八月十五日
聖母の被昇天
聖母被昇天には、聖母の清いご臨終が記念される。伝えによると、マリアは聖霊降臨後、十五年間、この世に留まられたと言われている。その間マリアは一種の寂しさとともに、いつかはおん子イエズスのおられる天国に昇れるという喜びを味わっていたにちがいない。人間にとって、喜びは、自分の欲するものが与えられたその時にあるとともに、与えられるのを今か今か待つ間にもある。
マリアは十五年の間一日一日と近づく永遠の幸福を思い、胸をときめかせながら、指折り数えてその幸福を待っていたことであろう。そして聖母は原罪も自罪もなく、あらゆる美しい徳に輝いた一生を送られたので、そのご死去はいかにもめでたいものであった。伝えによると、聖母は聖霊降臨後まもなく小アジア(今のトルコのエフェソに行き、十字架上におけるイエズスの遺言どおり、聖ヨハネの保護を受けながら余生を過ごされた。聖母のご死去の折り、世界に散らばって神のみ教えを伝えていた使徒たちは、聖トマ以外全員、聖母の枕元に集まってきて、最後の別れを告げた。今まで杖とも柱とも頼んでいた聖母に、いよいよ別れねばならぬかと思って、集まった人たちは非常に悲しんでいたので、聖母は彼らを慰めて、「私は天に昇っても決して、あなた方を忘れません。かえって生きているうちよりも、あなた方のためになるよう、取り次ぎをしてあげます」と約束された。やがておん子のお出迎えを受けて、平和な希望の中に快い愛熱に燃えつきて、眠るがごとく最後の息を引き取った。
聖母は神の特別のはからいで、原罪の汚れに染まらずに生まれた方であったから、かならずしも、ご死去なさらねばならぬはずでもなかった。でもおん子イエズスさえ、人びとを救うために、罪のないその体を、自由に十字架上のいけにえに献げたのに、自分ばかり死なずして天国に昇るのはいけないと考えられて、やはり人並みにご死去なさった。
それにしても聖母のご死去は、一般の人びとに見られるような、断末魔のもだえや苦しみを伴わず、何よりも楽しい、さいわいなご死去であった。マリアにとってそれは、長い間待ちこがれていた永遠の幸福への門出であり、天に在すおん父とおん子のもとに行くという喜びに満ちた死であったにちがいない。聖ベルナルドが言っているように、聖母のご死去は「天国への渇望の激しさに、その尊い霊魂が清い肉体を離れた」までにすぎなかった。
 使徒たちは聖母のご死去後、泣く泣くそのご遺体を墓に葬った。墓には三日の間というもの、絶えず天使らの奏でる楽しい音楽が聞こえ、ゆかしい香りが辺りにただよっていたという。三日日に音楽の音がハタとやんだ。
使徒たちは聖母のご死去後、泣く泣くそのご遺体を墓に葬った。墓には三日の間というもの、絶えず天使らの奏でる楽しい音楽が聞こえ、ゆかしい香りが辺りにただよっていたという。三日日に音楽の音がハタとやんだ。
ちょうどその時聖トマが来合わせ、せめて聖母のなきがらになりともお目にかかりたいと言うので墓を開いてみると、ご遺体は見えないで、ただご遺骸を包んだまき布だけが残っていた。そこで使徒たちは、聖母が、おん子と同じく三日日によみがえって天に昇ったものと、信ぜざるをえなかったそうである。これは伝説であるからどこまでが歴史的事実であるかはっきりしない。
しかし、一九五〇年(昭和二十五年)の諸聖人の祝日(十一月一日)にあたって教皇ピオ十二世は、聖母被昇天を信仰個条として次のように宣言した。「神の無原罪のおん母、柊生処女マリアが地上の生活を終えて霊魂と同時に身体をも天の光栄に上げられた」。
聖パウロがローマ書五章の十二節で「罪によつて死が入ったように、人はみな罪を犯したので、すべての人が死ぬようになった」と言うとおり、罪から死が生じ、死から腐敗が生じた。だから罪のないところには、死ぬこともなければ、死体が腐ることもない。
ところで、聖母マリアは無原罪のおん宿りの教義に照らしても明らかなように、原罪の汚れが少しもない。だから罪のない、その肉体は腐敗すべきものではなかったのである。ただし、聖母の死去は、前にも述べたように、おん子イエズスにならわれたためにほかならない。
また聖母はイエズスの十字架のもとに立たれ、悪魔の勢力と死に対し、雄々しく戦い、蛇の頭をくだいて罪と死に打ちかたれたのだから、人祖に課せられた「ちりにかえるであろう」という罪の罰を受ける筋合いはなかった。そのうえ聖母は、神のおん母としての特権から、すべての自罪をも犯しえないほどに神の恩恵に満ち満ちており、神のおん子を九か月間も宿したその清い身は、決して腐敗すべきではなかった。
聖ヨハネ・ダマスコも、以上の考えをまとめて美しく表現している。
「かつて九か月の間、創造主を納め奉った神の活ける聖櫃は、今、天の宮殿に迎え入れられたのである。かつて、その霊魂を以上の愛によって汚すことなく、その心を人間的情愛にしばられることなく、ひたすら天国をあこがれ続けていた無原罪の聖マリアは、今永遠のみ国に導き入れられたのである。生命そのものを世にもたらし奉った聖マリアが、死にたもうはずはなかった。けれども、聖母は第一のアダムの子として、死の宣告に服することを望まれた。生命そのものたるおん子も死を免れることを望みたまわなかったからである。聖母はいったんお墓に眠られたが、まもなく、生ける神のおん母として、そのおそばに呼び戻されたのであった。生命のもとなるキリストが、その生命を受けたもうた尊いおん体に、どうして腐敗の影のさし入ることが許されよう。……童貞をそこなうことなく、そのご胎内に宿ることを望みたもうと同じく、無原罪なる聖母のおん体が、死と腐敗とを免れて、人類の復活に先んじて、栄誉ある復活をなすことは、神のおん子の望みたもうところであった」と。
教会の聖人たち(中央出版社)/聖ステファノ王
八月十六日
聖ステファノ(ハンガリー)王
ハンガリーは十世紀の終わりころよりキリスト教国になったが、それは聖王ステファノのおかげにほかならない。この王はフン族出身であるが、フン族は、古代蛮族のなかでも、もっとも有力で、しかも多数の大集団を擁していた。現今残存するトルコ民族は、その流れを汲むもののうちで代表的なものであるが、一時彼らの征服範囲は、中国、朝鮮や、東南アジア諸地域まで延びていた。セルジュク・トルコ族はペルシャ地方を征服、オスマン・トルコと呼ばれる一族はサラセン帝国の東カリフを占領して、シリア、エジプト、ギリシャにまたがるオスマン・トルコ帝国を建てている。また一部の移動民族のうち、ゴート族についで、西ローマ帝国の滅亡に一役かってでたものである。古代のフン族はおおむねアジア系と∃ーロッパ系に分かれるが、ヨーロッパ系フン族は、ボルガ河流域に住みついて、フンガルと呼ばれるにいたった。このフンガル族の言語は、フン族のつかったことばの方言で、一説では両者ともコーカサス山麓に発祥したものと言われる。
ヨーロッパ征服を行なったフン族の首長アッチラは死して、この地にパンノニア国を残した。ローマ人は、この地をフンガリアと呼んだ。このフンガリア四代目の首長がゲィサ公で、彼はその下で使っていたある奴隷から、キリスト教の話を聞いた。それから、高徳の宣教師聖ウォルフガングなどから教理をくわしく教わり、しばらくしてその妻シャルロットおよぴ邸内の重臣たらといっしょに洗礼を受けたのである。ゲィサ公の妻シャルロットは、異常な熱意をもって完徳に向かって精進していったが、ある日夢のなかで最初の殉教者聖ステファノが現われ、彼らに子供がさずけられることを告げ、その子に自分と同じ名をつけることをすすめ、彼の将来についての予言を聞いた。九七七年、シャルロットは男子を産んでその名をステファノとし、四歳の時に洗礼をさずけてもらった。ステファノはプラーグの聖アダルベールの指導で聖会の教えや秘跡に育まれつつ、忍耐、柔和、堅忍不抜などの諸徳をつちかった。またテオダという貴族の家庭教師の指導により学問の道にも著しく進歩した。九九七年、父ゲィサ侯は臨終の枕べに二十入歳のステファノと重臣らを集め、「私が亡くなったあとは、ステファノを国王となし、これに忠誠を尽くしなさい」と遺言した。一同は感激して「おことばどおりいたします」と誓い、国民とともにステファノを新国王に選んだ。
青年国王のもっとも意を用いた政策は、隣国と平和を保つと同時にカトリックを人びとに信奉させることだった。しかし、まもなく王の政策に反感をいだいた二、三の領主が反乱を起こした。ステファノは大いに心配して一心こめて祈り、聖母マリア、聖マルチノ、聖ジオルジオの取り次ぎを願ってから出陣し、敵の根拠地ベスプリツ市を占領した。
敵軍の将兵をきわめて寛大に取り扱い、また戦勝感謝としてその地にマルチノ修道院を建てた。その後、他国に戦争をしかけられても自重し、できるだけ平和策を講じた。その後ステファノはドイツ皇帝ハインリッヒ二世の信仰あつい妹ギゼラを王妃に迎え、共に励まし合って信心業や修徳の道に精進した。またマルチンスベルクやその他に教会や修道院を建設したり、貧民を援助したりした。そのうえローマの教皇と交渉してハンガリー国内の教会を組織し、ストリゴニウムを首都の大司教に任命し、その下に高徳の司教を国内十区の司教区に配置して国を統一し、聖職者の生活を援助した。
ときの教皇シルヴェストロ二世は、王の教会に尽くした功労に報いるため、美しい王冠を贈られた。ここにステファノは千年の降誕祭に大司教の司式により盛大な戴冠式を行ない、公式にハンガリー最初の国王の位についた。この王冠は、その後の新王の戴冠式ごとに用いられ、今なお国宝としてブタペストに保存されている。
 ステファノはいそがしい国政のかたわら、教会を助け、自国だけではなく遠くエルサレム、コンスタンチノープル、ローマにも聖堂を建て、これを聖母に献げ、聖母の被昇天の祝日をハンガリーの国祭日と定めた。そして毎日黙想、祈り、ミサ聖祭、聖体訪問などにも数時間を費やし、自分の衣食住をきわめて質素にし、余分なものをすべて貧者に施した。その時には特別服装を質素にし、ひそかに城を出て行った。ある日のこと、同じように変装して寄付袋をさげて歩いていると、一人の男が突然王に体当たりをして地に倒し、なぐりつけた上、その袋を奪って逃げた。花と血に染まりながらも、王は静かに立ち上がり、逃げるのを追いもせず聖母に感謝したという.
ステファノはいそがしい国政のかたわら、教会を助け、自国だけではなく遠くエルサレム、コンスタンチノープル、ローマにも聖堂を建て、これを聖母に献げ、聖母の被昇天の祝日をハンガリーの国祭日と定めた。そして毎日黙想、祈り、ミサ聖祭、聖体訪問などにも数時間を費やし、自分の衣食住をきわめて質素にし、余分なものをすべて貧者に施した。その時には特別服装を質素にし、ひそかに城を出て行った。ある日のこと、同じように変装して寄付袋をさげて歩いていると、一人の男が突然王に体当たりをして地に倒し、なぐりつけた上、その袋を奪って逃げた。花と血に染まりながらも、王は静かに立ち上がり、逃げるのを追いもせず聖母に感謝したという.
その後、敵の侵入が相次いで起こり、王の平和工作にもかかわらず、つごう三回敵と戦火を交え、若い王子を三人も戦場で亡くした。残ったのはエメリヒという王子ただ一人になった。この青年王子は父に似て、徳高く聖なる生活を送っていた。それで皇室も国民も、ステファノの申し分ない後継者になれるものと大いこ期待をかけていた。ところが惜しくもエメリヒは父に先立つこと七年、急病をわずらって、そのまま帰らぬ人となった。その時のステファノ王の悲嘆はどんなだったであろう。ただ多少の慰めとなったのは、エメリヒの取り次ぎで多くの奇跡が行なわれたことであった。
その後もステファノ王は、公僕として神と国民に奉仕し、晩年の長い病苦にもよく忍耐した。一〇三八年、臨終の直前に、重臣、司教らを枕べに招き、おいのペトロを王位継承者と定め、幾皮も聖母のみ名を呼びながら静かに永眠した。遺件はブタペスト聖堂内の聖エメリヒのかたわらに葬られた。
死後四十五年にして、早くも子のエメリヒとともに聖人の列に加えられた。王の葬儀の日、八月二十日は今なおハンガリーの首都ブタペストで盛大に行なわれている。王の右手は今も腐敗せず、首都の城内礼拝堂に保管され、人びとの崇敬の的となっている。
目次に戻る
.pl?jstephn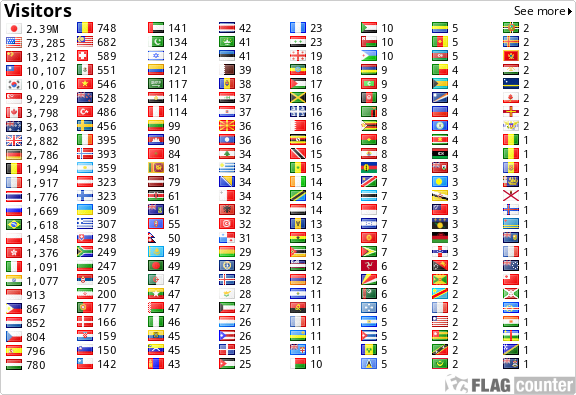
 使徒たちは聖母のご死去後、泣く泣くそのご遺体を墓に葬った。墓には三日の間というもの、絶えず天使らの奏でる楽しい音楽が聞こえ、ゆかしい香りが辺りにただよっていたという。三日日に音楽の音がハタとやんだ。
使徒たちは聖母のご死去後、泣く泣くそのご遺体を墓に葬った。墓には三日の間というもの、絶えず天使らの奏でる楽しい音楽が聞こえ、ゆかしい香りが辺りにただよっていたという。三日日に音楽の音がハタとやんだ。 ステファノはいそがしい国政のかたわら、教会を助け、自国だけではなく遠くエルサレム、コンスタンチノープル、ローマにも聖堂を建て、これを聖母に献げ、聖母の被昇天の祝日をハンガリーの国祭日と定めた。そして毎日黙想、祈り、ミサ聖祭、聖体訪問などにも数時間を費やし、自分の衣食住をきわめて質素にし、余分なものをすべて貧者に施した。その時には特別服装を質素にし、ひそかに城を出て行った。ある日のこと、同じように変装して寄付袋をさげて歩いていると、一人の男が突然王に体当たりをして地に倒し、なぐりつけた上、その袋を奪って逃げた。花と血に染まりながらも、王は静かに立ち上がり、逃げるのを追いもせず聖母に感謝したという.
ステファノはいそがしい国政のかたわら、教会を助け、自国だけではなく遠くエルサレム、コンスタンチノープル、ローマにも聖堂を建て、これを聖母に献げ、聖母の被昇天の祝日をハンガリーの国祭日と定めた。そして毎日黙想、祈り、ミサ聖祭、聖体訪問などにも数時間を費やし、自分の衣食住をきわめて質素にし、余分なものをすべて貧者に施した。その時には特別服装を質素にし、ひそかに城を出て行った。ある日のこと、同じように変装して寄付袋をさげて歩いていると、一人の男が突然王に体当たりをして地に倒し、なぐりつけた上、その袋を奪って逃げた。花と血に染まりながらも、王は静かに立ち上がり、逃げるのを追いもせず聖母に感謝したという.